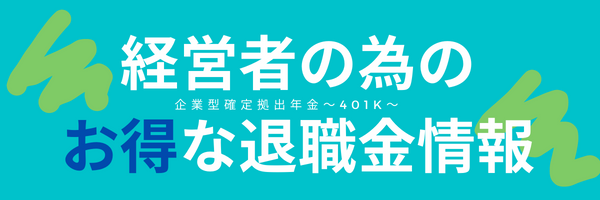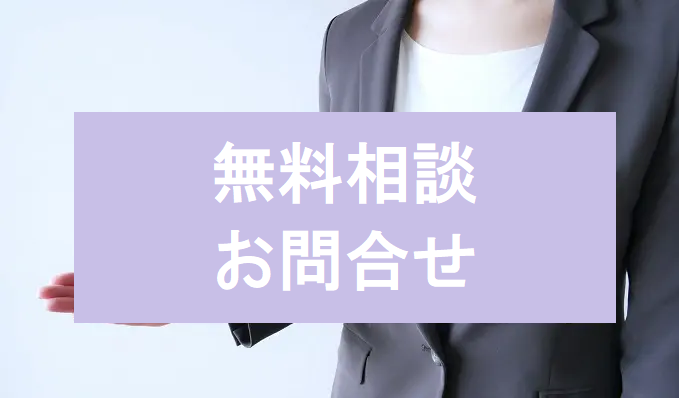【コラム】従業員のメンタル不調に早期に気づき、適切に対応するために
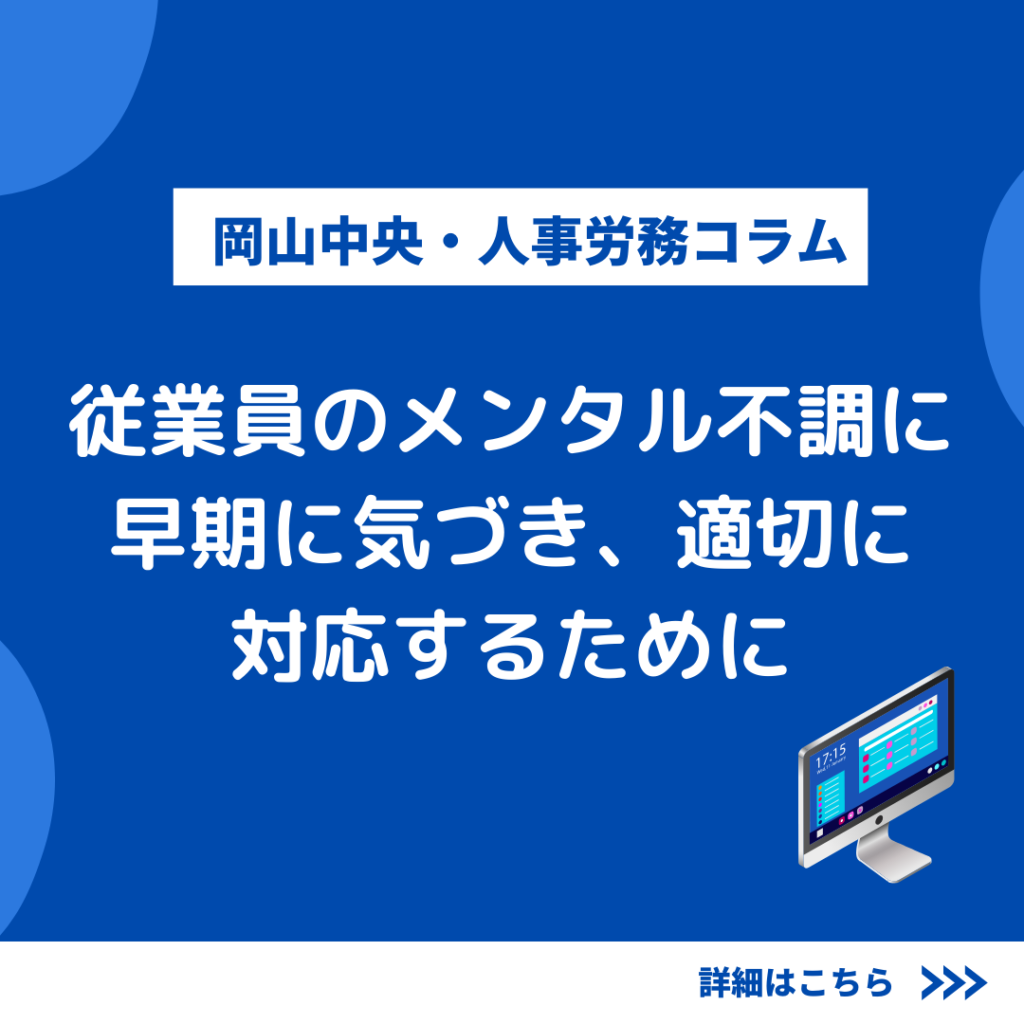
従業員のメンタル不調は、企業のパフォーマンスや職場環境に大きな影響を及ぼす可能性があります。そこで、早期に兆候を察知し、適切に対応することが非常に重要です。本記事では、従業員のメンタルダウンに気づき、対応を進める際のポイントを解説します。個別の事案による違いもありますので、詳細についてはぜひ弊社までご相談ください。
メンタルダウンの兆候に気づく
メンタルダウンには必ずステップがあります。以下の段階を把握し、早期発見を心がけましょう。
-
メンタル面の不調(元気がない、落ち込みなど)
-
身体面での不調(眠れない、頭痛などの身体症状)
-
行動の変化(遅刻や欠勤、ミスの増加など、周囲から見て明らかにわかるレベル)
早期に気づき対応することで、従業員が職場に復帰しやすくなり、予後も良好です。
状況の正確な見極めがカギ
まず、現在の従業員がどの段階にいるのかを正しく見極めることが必要です。
その上で、会社と本人が納得する形で対応を進めていきます。以下の流れをご参考にしてください。
1. 会社としての考えを明確にする
- メンタル不調の従業員をどのようにサポートするのか、会社の方針や体制を整理・共有します。
2. 本人の意向を確認する
- 現状についての本人の考えや希望をヒアリングします。「今どうしたいか」を明確にすることがポイントです。
3. 選択肢を提示し、本人に選ばせる
以下のような選択肢を検討し、本人と相談の上で対応を進めます。
1. 勤怠やパフォーマンスの改善
双方で以下の3点を同意しておきます。
- どのレベルまで改善するか
- いつまでに達成するか
- 目標が達成できない場合の対応
ポイント:
この選択肢は、現在のポジションを維持しつつ早期復帰を目指すものです。ただし、本人に過度な負担をかけないよう、段階的な改善計画を立てることが重要です。
2. 休職しコンディションを整える
本人の健康状態が改善するまで一定期間の休職を提案する選択肢です。
具体的なサポート例:
- 休職制度の適用について詳細を説明する(期間、手続き、給与の有無など)
- 休職中も必要に応じて会社側からのフォローやサポートを提供する(カウンセリングの手配、定期的な連絡など)
- 休職明けの復帰プランを事前に検討し、復帰後の働き方を柔軟に調整する
ポイント:
休職は従業員の健康を第一に考えた対応であり、無理なく回復をサポートすることが重要です。復職時にスムーズに業務に戻れる環境整備も忘れずに行いましょう。また、見落としがちですが会社の休職規程について会社の現状に即した内容になっているか確認しましょう。(いざという時のために、早めに専門家に確認を取っておく必要があります。)
3. 職位や契約条件の変更
現行のポジションや業務内容に大きな負担がある場合、職位の変更や契約条件を見直す選択肢です。
具体的なサポート例:
- 業務内容や責任範囲を見直し、負担軽減を図る
- 時短勤務やフレックスタイム制の活用を提案する
- 必要に応じてチーム内での役割を再編成し、本人が負担なく業務に取り組める環境を作る
ポイント:
従業員が心身ともに健康な状態で働き続けられるよう、柔軟な対応を心掛けましょう。変更内容について、本人としっかり合意することが大切です。
4. 新しいキャリアを模索して退職する
本人が新しいキャリアに進む意思がある場合には、円満退職をサポートします。
具体的なサポート例:
- 再就職支援(必要に応じてキャリアコンサルティングの提供や就職支援サービスの案内)
- 退職後の手続きやスケジュールの明確化(退職金や保険、年金の手続きなど)
- 本人の気持ちに寄り添い、退職理由をポジティブに整理するサポート
ポイント:
退職を選択する場合も、前向きな形で次のステップを踏み出せるよう、丁寧に対応しましょう。会社のイメージにも影響するため、円満な退職を目指すことが重要です。
会社の安全配慮義務違反を問われないために
従業員のメンタル不調に適切に対応することは、会社の安全配慮義務を果たすうえでも重要です。メンタル不調が労災認定される基準は、厚生労働省の資料(労災認定基準はこちら)で具体的に示されています。裏を返せば、この基準を意識した労務管理を心掛けることで、労災認定を防ぎつつ、適切な対応を行うことが可能です。
以下のポイントを意識して管理を行いましょう:
- 過重労働を避ける
長時間労働や極端な業務負荷がないかを定期的にチェックし、早期に是正する。 - 適切な職場環境の整備
パワーハラスメントや職場内での不適切な対応を防ぐ仕組みを導入する。 - 従業員の健康状態を把握
ストレスチェックの実施や、定期的な面談を通じて早期に兆候を察知する。 - 相談窓口や対応フローの整備
従業員が安心して相談できる環境を提供し、迅速に対応する体制を明確にする。
これらを実施することで、万が一メンタル不調の従業員が出た場合でも、会社としての対応責任を果たした証拠となります。適切な対応を怠った場合、安全配慮義務違反として法的責任を問われるリスクがあるため注意が必要です。
まとめ
従業員のメンタル不調に対する対応は、一律の解決策があるわけではありません。
本人の状態を正しく理解し、会社としての方針を明確にしつつ、適切な選択肢を提示することで、従業員も会社も納得感のある形で進めることができます。
弊社では、従業員のメンタルヘルスに関するご相談や、具体的な対応策のアドバイスを行っています。個別の事案についてはぜひお気軽にお問い合わせください。