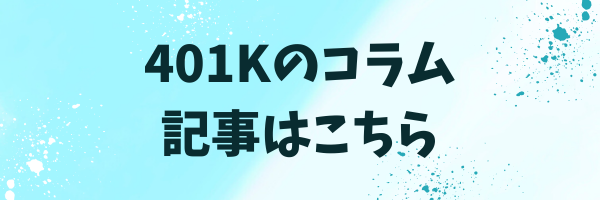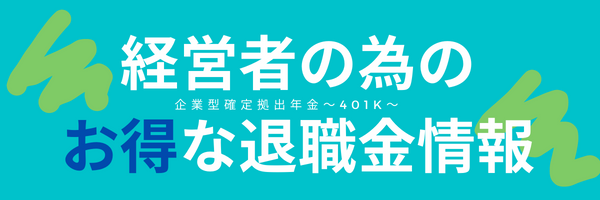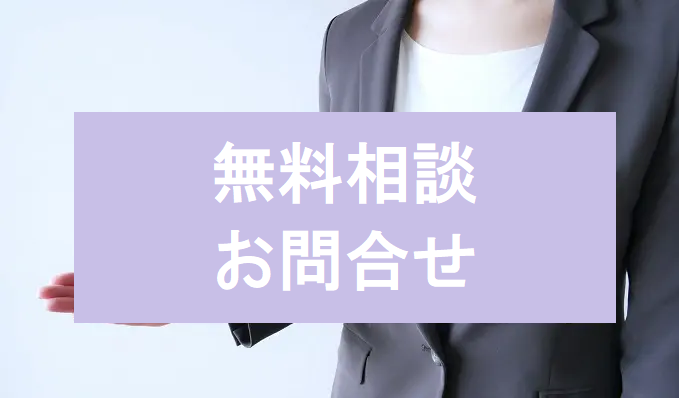【DCコラム】従業員の退職金制度を考える経営者の使命|社労士 岡山・倉敷
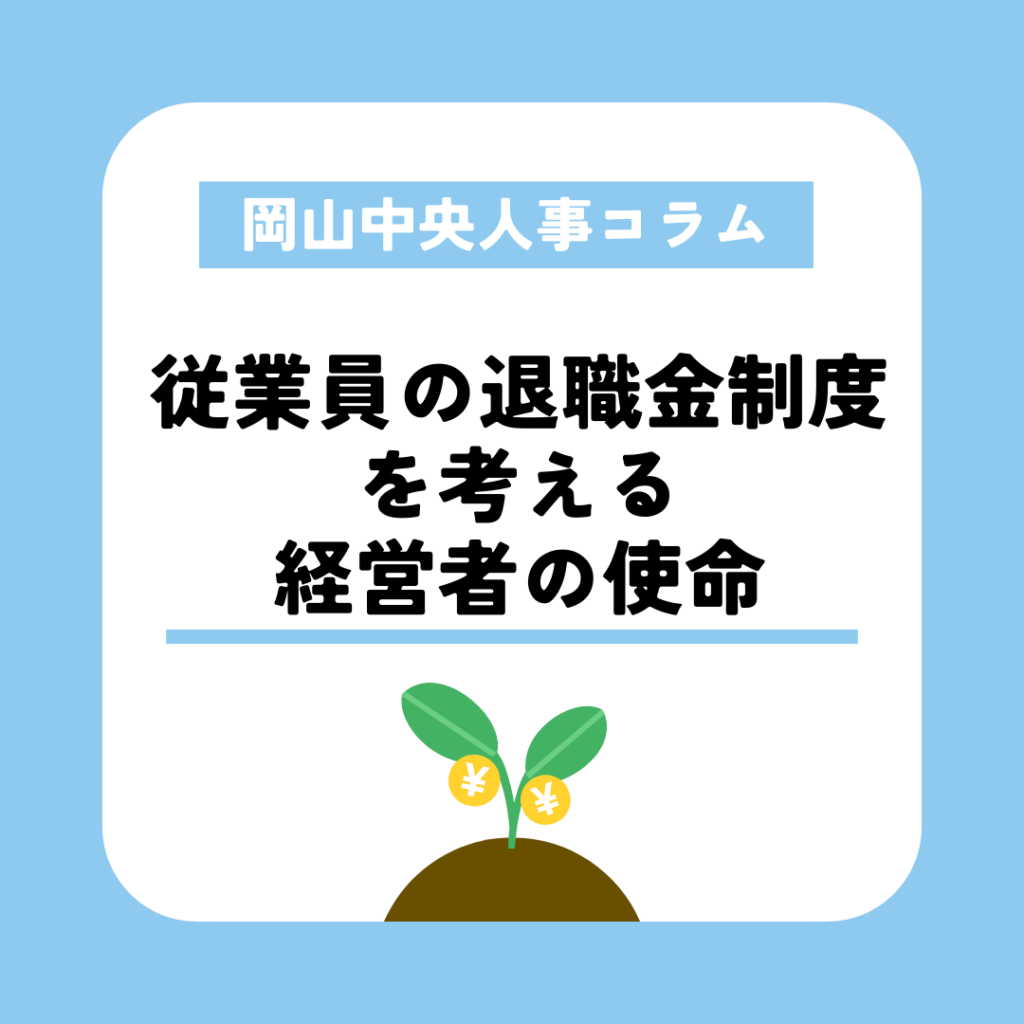
近年、従業員の老後資金を確保するための退職金制度が企業の重要な役割となっています。金融リテラシーが高く、自身でiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している従業員もいますが、その割合はごく少数であり、大半の従業員にとって退職金は重要な生活基盤となります。
そこで、企業として従業員に適切な退職金制度を提供することが、経営者としての使命と言えるでしょう。今回は、中小企業退職金共済(以下、中退共)と企業型確定拠出年金(以下、企業型DC)の比較を通じて、最適な退職金制度について考えてみましょう。
中退共と企業型DCの比較
以下の表に、中退共と企業型DCの主な特徴をまとめました。
| 項目 | 中退共 | 企業型DC |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 退職時に一時金を支給 | 老後の年金資産を形成 |
| 掛金助成 | 新規加入時に1年間助成あり | 助成金なし |
| 役員の加入 | 不可 | 可能 |
| 運用利回り | 約1% | 平均約3%(個人の運用成績による) |
| 中途退職時の返還 | 掛金の全額が従業員に支給 | 制度設計によっては事業主返還設定が可能 (勤続3年未満の場合) |
中退共は国の助成金があり、運用リスクが低いという利点があります。一方、企業型DCは運用の柔軟性が高く、インフレに対応した運用が可能であるため、将来の退職金の価値を維持しやすいという特徴があります。また、企業型DCは役員も加入可能であり、経営層の老後資金形成にも対応できる点が魅力です。
インフレ局面でなぜ企業型DCが適しているのか?
物価が上昇するインフレ局面では、お金の価値が下がり、固定的な利率で運用される退職金制度では将来の受け取り額の実質的な価値が目減りする可能性があります。たとえば、今の1万円で買えるものが10年後には1万5千円必要になる、といった状況が起こり得ます。
企業型DCでは、従業員が掛金を投資信託や株式、債券などで運用することが可能であり、物価上昇に見合ったリターンを狙うことができます。特に、平均3%程度の利回りが期待できるため、インフレによる価値の目減りを防ぎやすい仕組みです。
さらに、企業型DCは会社が制度を整えた上で、従業員は「会社が掛けてくれる金額で運用するか」「給料として受け取るか」を選べる仕組みを作ることが可能です。これにより、金融知識がなくても簡単に運用を始められる点がメリットです。
時代は企業型DCへ
政府は老後資金の確保を支援するため、iDeCoや企業型DCなどの税制優遇制度を拡充しています。来年度の税制改正案では、企業型DCやiDeCoの拠出限度額が引き上げられる方向にあります。この背景には、インフレリスクの高まりがあり、従業員の実質的な退職金価値を守るために、より高い運用利回りが求められているのです。
企業型DCでは、従業員が自分の掛金を追加できる柔軟な仕組みを持ち、掛金や運用内容を個々の状況に応じて選択可能です。このため、会社として標準的な掛金額を設定し、「積み立てる」「給与として受け取る」の2択を提示する制度設計も可能です。これにより、多くの従業員が参加しやすくなります。
まとめ
企業型DCは、企業が従業員に対して提供できる柔軟で将来性のある退職金制度です。中退共と比較して運用利回りが高く、経営者や役員も加入可能な点で、企業全体の福利厚生を向上させる強力なツールとなります。時代の流れに対応し、従業員の安心した老後を支える制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
企業型DCや退職金制度の詳細についてのご相談は、社会保険労務士である弊社までお気軽にお問い合わせください。