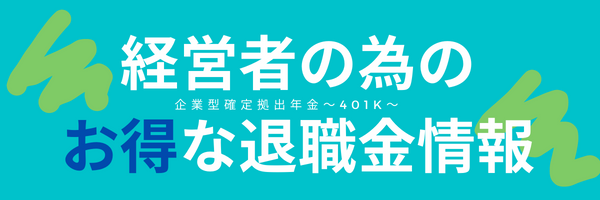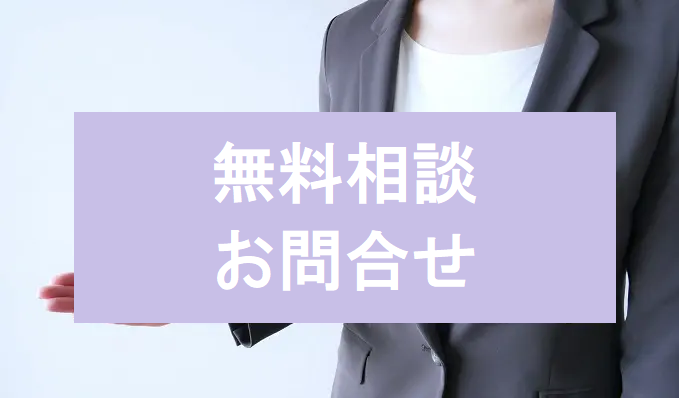【人事労務コラム】令和8(2026 )年1月1日から労働安全衛生法が改正されます!|社労士 岡山・倉敷
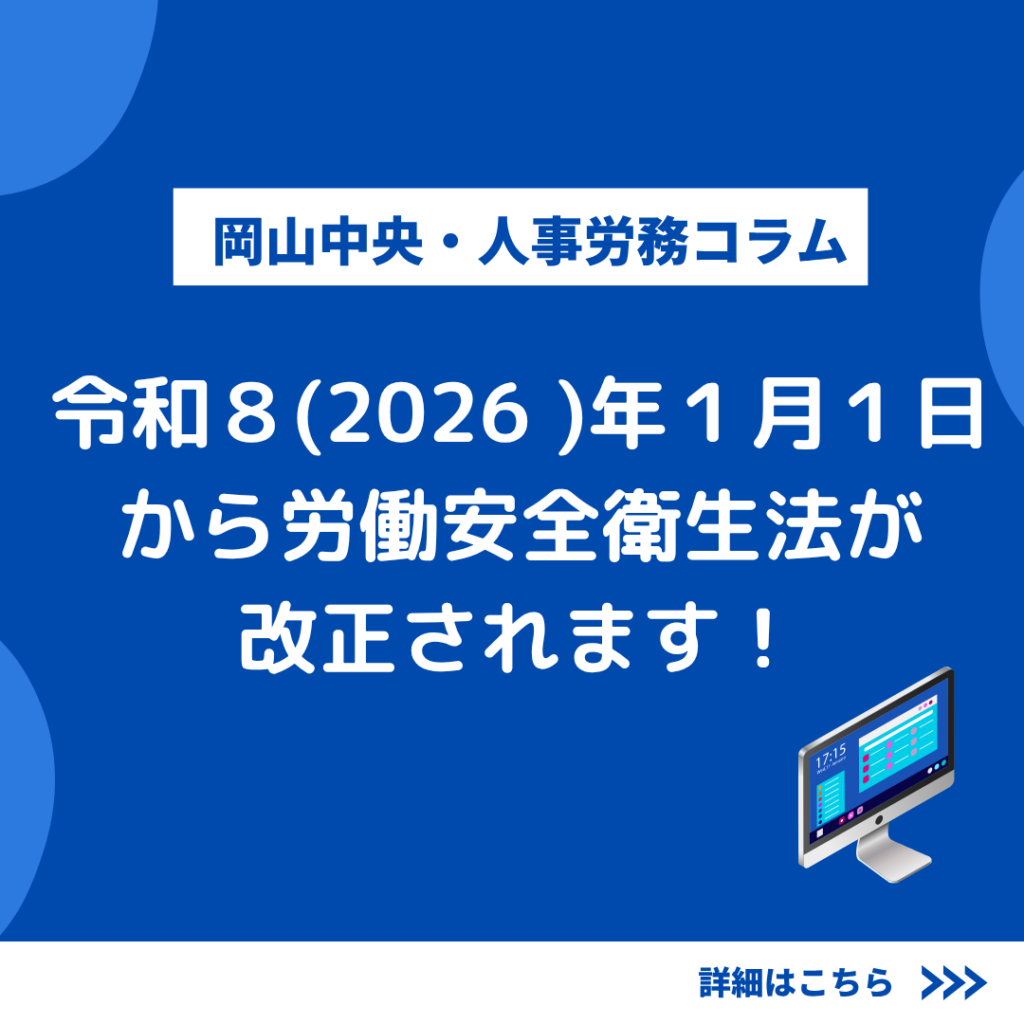
~6つの注目ポイントをわかりやすく解説~
2025年5月14日に「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」の改正が公布され、2026年1月1日から順次施行されることになりました。(労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号))
今回の改正では、労働災害の防止や働く人の健康を守るために、6つの重要なポイントが盛り込まれています。
この記事では、それぞれの内容を、前提・背景・改正内容に分けてわかりやすく解説します。
① 個人事業者などへの安全衛生対策の支援
■前提:
これまで労働安全衛生法の対象は「労働者」に限られていました。しかし、現場では**フリーランスや一人親方(個人事業主)**も一緒に働いていることが多く、安全面での課題がありました。
■背景:
実際に災害に遭っているのは、労働者だけではありません。とくに建設現場などでは、個人事業主が事故に巻き込まれるケースも見られています。
■改正内容:
国が、個人事業主や中小企業に向けて安全衛生対策を支援する仕組みを明文化しました。
たとえば、安全教育の提供や保護具の使用の推進などが含まれます。
② メンタルヘルス対策の推進
■前提:
働く人の「こころの健康」を守るため、現在もストレスチェック制度がありますが、うつ病や適応障害などの労災申請は増加傾向にあります。
■背景:
制度があっても、うまく活用されていない職場も多く、より積極的な対策が求められていました。
■改正内容:
企業に対し、メンタルヘルス対策を努力義務として明記しました。
相談体制の整備や研修、外部専門家の活用などを通じて、こころの健康を守ることが期待されます。
③ 化学物質による健康障害の防止強化
■前提:
作業現場では、有機溶剤や粉じんなどの化学物質による健康リスクがあります。目に見えないため、対策が遅れがちでした。
■背景:
がんや中毒などの健康被害を未然に防ぐためには、現場ごとのリスク評価(リスクアセスメント)が欠かせません。
■改正内容:
-
危険な化学物質を、政令でスピーディに規制対象に追加可能に
-
譲渡・提供時にもリスクアセスメントを義務化
-
ラベル表示やSDS(安全データシート)の徹底
-
化学物質管理者の選任対象を拡大(※2026年4月~)
👉ポイント:「使う側」だけでなく「提供する側」にも責任が生まれます。
④ 機械による災害を防ぐしくみの強化
■前提:
製造現場などでは、機械への「巻き込まれ」や「はさまれ」事故が今も多く発生しています。
■背景:
古い設備や、安全装置のない機械がそのまま使われているケースもあります。また、設計段階での安全対策が不十分なことも原因の一つです。
■改正内容:
厚生労働大臣が、機械の設計者や製造者に対し、安全への配慮を勧告できる制度が新設されました。
現場だけでなく、「設計段階」から災害を防ぐアプローチです。
⑤ 高年齢労働者の労災防止の推進
■前提:
定年延長などで、60歳以上の労働者が増えています。ところが、労災の約4割が高年齢者に集中しているというデータがあります。
■背景:
加齢に伴う体力や反応速度の低下により、転倒・墜落・誤操作などの事故が起きやすくなります。
■改正内容:
企業に対し、高齢者の安全対策を努力義務として明記しました。
作業内容の工夫や教育方法の見直しなどが求められます。
⑥ 治療と仕事の両立支援
■前提:
がん、糖尿病、精神疾患、妊娠出産など、通院や治療をしながら働く人が増えています。
■背景:
職場の理解や柔軟な勤務体制がないと、治療と仕事を両立できずに退職を余儀なくされるケースが少なくありません。
■改正内容:
企業に対し、治療と仕事の両立支援を努力義務化。
主治医と連携して勤務調整を行う、本人の申出を受けて相談体制を整えるなどの取り組みが期待されます。
まとめ
今回の改正は、「義務の強化」よりも、「事業者が自主的に取り組むための支援や方向性を明確化する」ことに重きが置かれています。
中小企業や現場の担当者にとっても、今回の改正を機に、
-
安全衛生体制の見直し
-
メンタルや高齢者への配慮
-
化学物質や機械のリスク管理
を進めることが求められています。
ご不明点があれば、当事務所までお気軽にご相談ください。