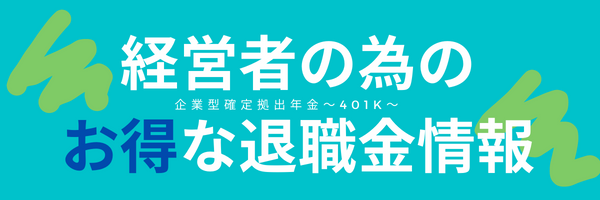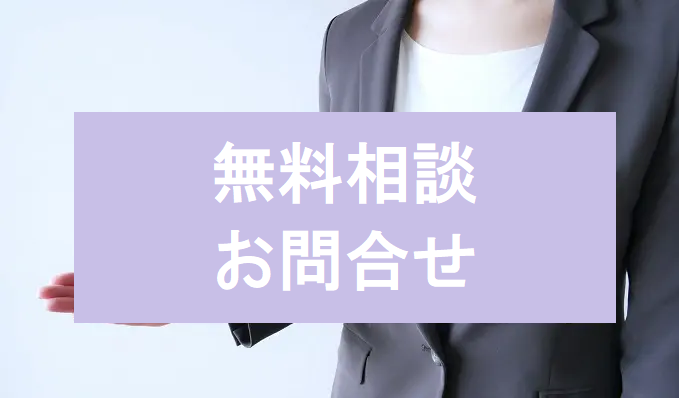【人事労務コラム】有期雇用契約の「自動更新」って本当に大丈夫?~実質“無期契約化”のリスクと、見直したい契約条項~|社労士 岡山・倉敷
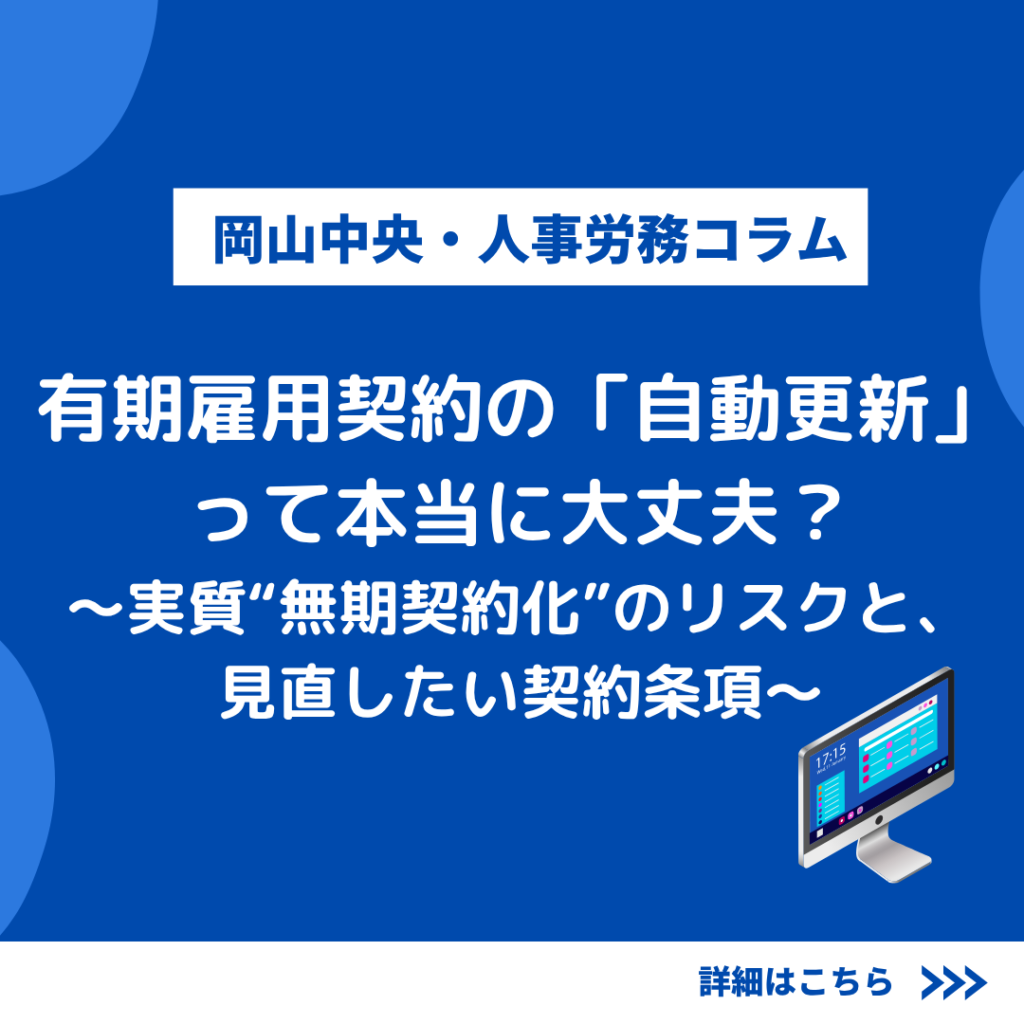
「期間の定めがある契約だけど、特にトラブルもないし、自動更新にしておこう。」
そんな契約書、思い当たる企業も多いのではないでしょうか。
実はこの「自動更新」という一文、
法律上はすぐに違法というわけではありませんが、実務的にはリスクを抱えた表現です。
最近は、行政の指導でもこの点が厳しく見られるようになっています。
※ ※ ※
1.「自動更新」契約のどこが問題なのか?
有期雇用契約は、「〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで」と契約期間を明示し、
さらに「更新の有無」や「更新の判断基準」をあらかじめ知らせる必要があります。
これは労働基準法第15条、労働契約法第4条で定められています。
ところが、「自動更新とする」と書かれている契約では、
更新の可否や条件があいまいになりがちです。
結果として、実態が“期間の定めのない雇用”と変わらなくなる場合があります。
※ ※ ※
2.実際に起きたトラブルや裁判例
長期間にわたり更新を繰り返すと、
裁判では次のように判断されるケースがあります。
更新を前提に長く勤務していたなら、
形式上は有期契約でも、実質的には“期間の定めのない契約”とみなす。
(学校法人日立学園事件・最判平成15年10月10日)
つまり、「自動更新」を重ねていくほど、
会社が「契約を更新しない」と言いづらくなり、雇止めが実質的に“解雇扱い”になる可能性も。
※ ※ ※
3.2024年の法改正でも「更新の明示」がより重要に
2024年4月からは、労働条件の明示事項が改正され、
契約更新の判断基準を具体的に記載することが求められています。
たとえば次のような書き方が望ましいとされています。
更新の有無:あり(更新する場合がある)
更新の判断基準:勤務成績・業務量・会社の経営状況等を総合的に勘案して判断する。
単に「自動更新」とするだけでは、
この明示義務を満たしていないと見なされるおそれがあります。
※ ※ ※
4.無期転換ルールにも注意を
労働契約法第18条では、
有期契約が通算5年を超えて更新された場合、
労働者が申し込めば「無期雇用に転換」できる制度(無期転換ルール)が定められています。
ここで誤解されやすいのがこの点です👇
ちなみに、無期転換ルールは「労働者の申し出」があった場合に適用される制度です。
会社側から「次の契約から無期にします」と自動的に案内する義務まではありません。ただし、その判断や更新の運用がスムーズに行えるように、
2024年改正で「更新条件の明示」が義務づけられた、という背景があります。
つまり、「自動的に無期化するわけではないけれど、
更新の運用があいまいなままだとトラブルにつながる」――という点を理解しておくことが重要です。
※ ※ ※
5.経営者が今できる見直しポイント
| チェック項目 | 対応のポイント |
|---|---|
| 契約書に「自動更新」とだけ書かれていないか? | 「更新する場合がある」に修正し、判断基準を明示する |
| 更新の都度、契約内容を見直しているか? | 定期的に面談・評価を行い、更新可否を記録しておく |
| 無期転換ルールの対象者を把握しているか? | 契約管理台帳などで通算期間を確認する |
6.まとめ
「自動更新だから安心」と思っていた契約が、
実は“更新拒否できない契約”になっていることもあります。
契約書の見直しは、
「トラブル予防」と「法改正対応」の両面から今こそ重要です。
当事務所では、有期契約書の点検や、更新条項の修正提案も行っています。
契約の更新回数・上限・判断基準など、
現場の実態に合わせた形に整えることで、無用なトラブルを防ぐことができます。
「うちの契約書、このままで大丈夫?」と感じたら、
どうぞお気軽にご相談ください。
※ ※ ※